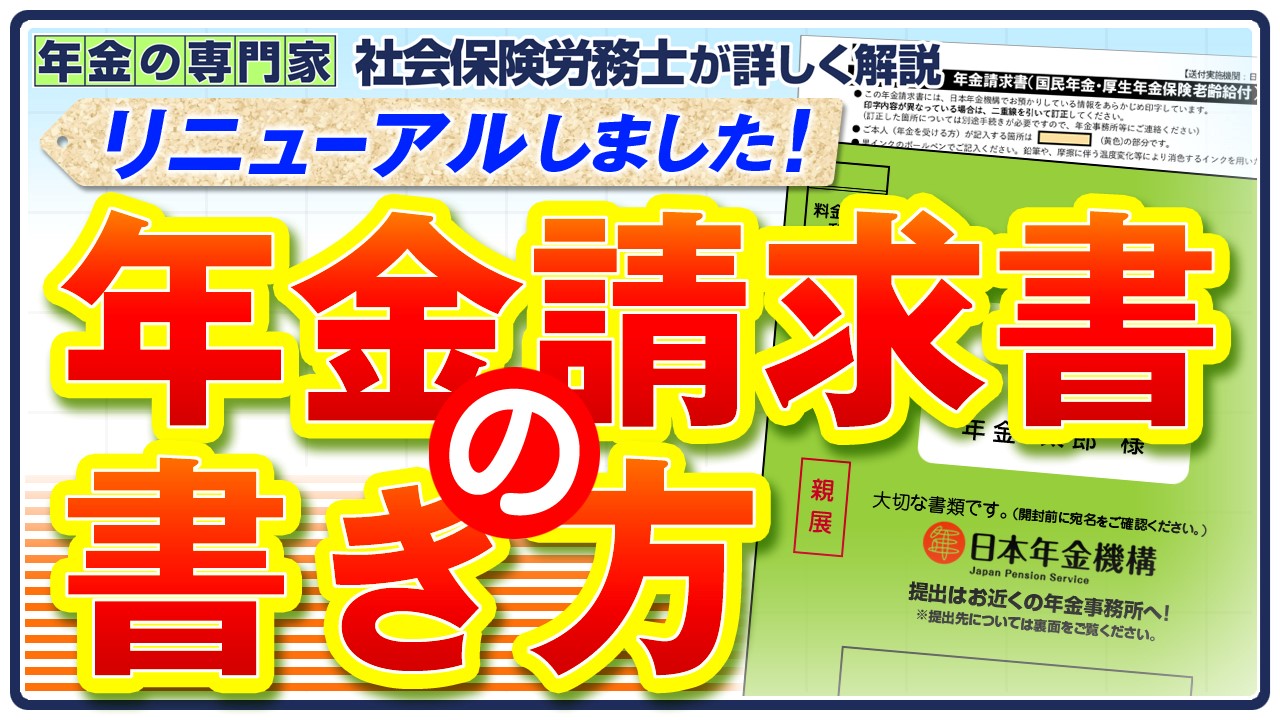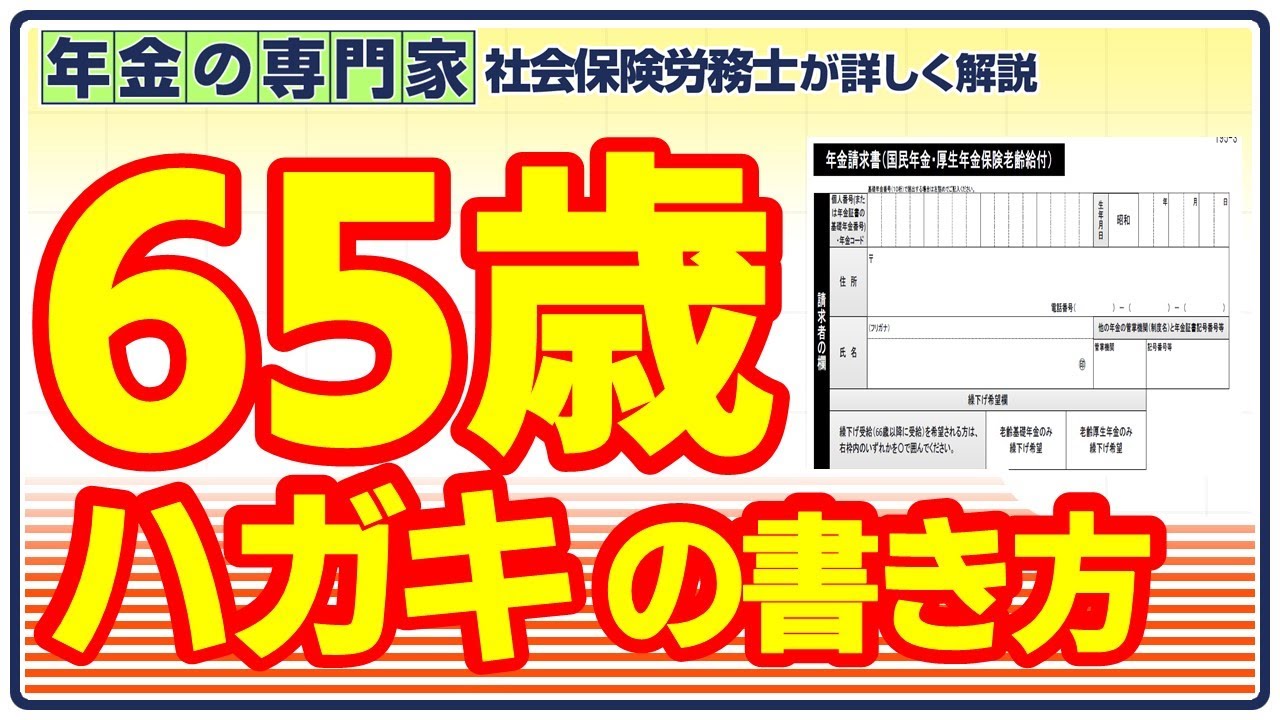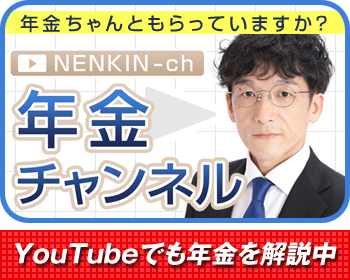年金請求書は、年金が受給できる年齢になる約3ヶ月前に、緑色の封筒で送られてくる書類です。
90%以上の人は本記事を見ながら記入いただければ簡単に完成すると思います。
※一部の人は年金事務所への確認が必要になるのでご了承ください。
【著者プロフィール】
・社会保険労務士 田島透
・YouTubeで年金チャンネルを運営中
・チャンネル登録者数は8万人
目次
年金請求書の記入方法をページごとに解説

年金請求書の記入方法をページごとに解説します。
まずは、お手元に黒のボールペンと年金請求書をご準備ください。
消せるボールペンは使用できません。
印鑑は不要ですので、もし記入間違いがあっても訂正印は必要なく、二重線で消して書き直してください。
1ページ目(住所、氏名、振込口座)

住所、氏名、年金振込口座を記入するページです。
住所・氏名・電話番号の記入方法

赤字で書いてある部分に記入が必要です。
住所の欄は、ふりがなをカタカナで書きます。
次に名前・電話番号を記入してください。
メモ
住所や名前に変更がある方は、印字されているところを二重線で消して書き直しましょう。
年金振替口座の記入方法
年金振替口座の記入方法です。

ゆうちょ銀行以外の場合は、左上の受取機関の「1.金融機関」に丸をしてください。

ゆうちょ銀行を選ぶ際は、上の画像の通り「2.ゆうちょ銀行」に丸をします。
口座記入欄の注意点は以下の通りです。
- 年金の振込口座は必ず年金請求者名義でなければならない
- 請求者のフリガナと口座名義のフリガナが相違していると振り込みエラーになる
- 右下の銀行の証明欄には届出印を押さない(銀行が証明印を押すところ)
希望の年金受取機関に該当する方を参考にしながら記入してください。
3ページ目(年金の加入記録)

加入記録を確認するページです。

赤枠の年金制度に書かれている制度に対応する記号を丸で囲みます。
4ページ目(年金の加入記録、旧姓、元配偶者)

年金の加入記録、旧姓、元配偶者を記入するページです。

3ページ目に記入されている以外の年金に加入した期間があれば書いてください。
旧姓がある場合は下の欄に記入が必要です。

4ページの下部に移ります。
(5)は受給資格期間が300ヶ月ない場合に記入が必要です。

受給資格期間は3ページ下部から確認できます。
メモ
記入する必要がある方(300ヶ月ない方)は、年金記録の確認のために年金事務所で相談するのがおすすめです。

元配偶者の情報を分かる範囲で記入してください。
現在の配偶者は8ページで書く欄があるため、ここで記入する必要はありません。
6ページ目(年金の受給歴、雇用保険の加入歴)
年金の受給歴、雇用保険の加入歴を記入するページです。
公的年金の受給状況を記入
公的年金の受給状況を記入してください。

現在何も受給していなければ上の画像と同じように「2.受けていない」に丸をして次に進みます。

公的年金を受給されている場合は「1.受けている」に丸をしてください。
企業年金などは記入する必要はありません。
サンプルとして遺族厚生年金を受給されている方の記入例を載せておきます。
こちらは正確にわからなくても大丈夫です。

あまりいないと思いますが、この請求書を提出する前に何か別の年金を請求している場合は「3.請求中」を選んで記入してください。
雇用保険の加入状況を記入
6ページの下に移ります。
雇用保険に関する記入事項です。
記入方法を3パターンご紹介します。
雇用保険に加入中、または抜けて7年経過していない場合

今までに雇用保険に加入したことがある方で以下に当てはまる場合は、上の画像を参考にしてください。
- 現在も加入中
- 雇用保険の被保険者ではなくなってから7年経っていない
2つのどちらかに該当する方は「雇用保険に加入したことがありますか」は「はい」に丸をします。
次に雇用保険の被保険者番号を記入します。
「60歳から65歳までに雇用保険から給付を受けたことがありますか」は「はい」または「いいえ」のどちらか当てはまる方に丸をしてください。
雇用保険を抜けて7年以上経過している場合

雇用保険に加入したことがあって、雇用保険の被保険者ではなくなってから7年以上経っているパターンです。
「雇用保険に加入したことがありますか」は「はい」に丸をします。
次に事由書の「ウ」に丸をして署名をしてください。
雇用保険に加入したことがない場合

次は、雇用保険に加入したことがない場合の記入方法です。
「雇用保険に加入したことがありますか」は「いいえ」に丸をします。
事由書の「ア」または「イ」に丸をして署名をしてください。
8ページ目(配偶者、子の情報)

配偶者、子の情報を記入するページです。

配偶者なしの場合は「いいえ」に丸をして、14ページ(年金、マイナンバー)に進んでください。

配偶者ありの場合は、赤枠を記入してください。
年金花子さんの記入サンプルを載せておきます。
基礎年金番号やマイナンバーが不明の場合、記入は不要です。
メモ
住所の記入欄は、夫婦の住民票住所が相違する場合のみ記入してください。
住所が相違するケースでは別途書類が必要なので年金事務所で確認しましょう。
配偶者の情報の記入が完了したら、8ページの下に移ります。

配偶者の年金の受給状況を記入してください。
分からなければ書かなくても大丈夫です。
サンプルとして特別支給の老齢厚生年金を受けている場合を記入しておきました。

子の記入欄については、以下の3つの条件を同時に満たしている場合に記入してください。
- 年金の請求者が配偶者加給年金をもらえる
- 配偶者加給年金がもらえるタイミング
- 18歳未満の子供がいる
言いかえるとほとんどの人が「65歳になったときに18歳未満の子どもがいるかどうか」ということです。
10ページ目(配偶者加給年金)

配偶者加給年金に関する内容を記入するページです。
配偶者加給年金については、こちらの記事で詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。


年金の請求者(年金請求書を出す人)が厚生年金や共済年金に20年以上加入がある場合に、請求者の名前を記入してください。
配偶者の名前を書く欄ではありません。
請求書を出すタイミングで加入期間が20年なかったとしても、これから加入して20年になる見込みがある場合も記入してください。

配偶者加給年金の対象になる配偶者や子の年収について、850万円未満なら「はい」に丸をします。
メモ
もし850万円を超えていて「いいえ」に丸をする場合は年金事務所でご相談ください。
14ページ目(年金番号、マイナンバー)

年金番号やマイナンバーを記入するページです。

基礎年金番号以外に年金手帳の番号がある場合に記入します。
基礎年金番号に統合されている番号は記入不要です。

次はマイナンバーの記入欄です。
マイナンバーが未登録の場合、記入すると住民票などの添付書類を省略できます。
記入は必須ではありません。

特別一時金を受けたことがなければ「いいえ」に丸をしてください。
ほとんどの人は、特別一時金を受けたことがないと思います。

配偶者が、基礎年金番号と異なる記号番号の年金手帳をお持ちの場合は記入してください。
16ページ目(振替加算)

振替加算に関する内容を記入するページです。
振替加算の基本については、以下の記事で詳しく解説しています。
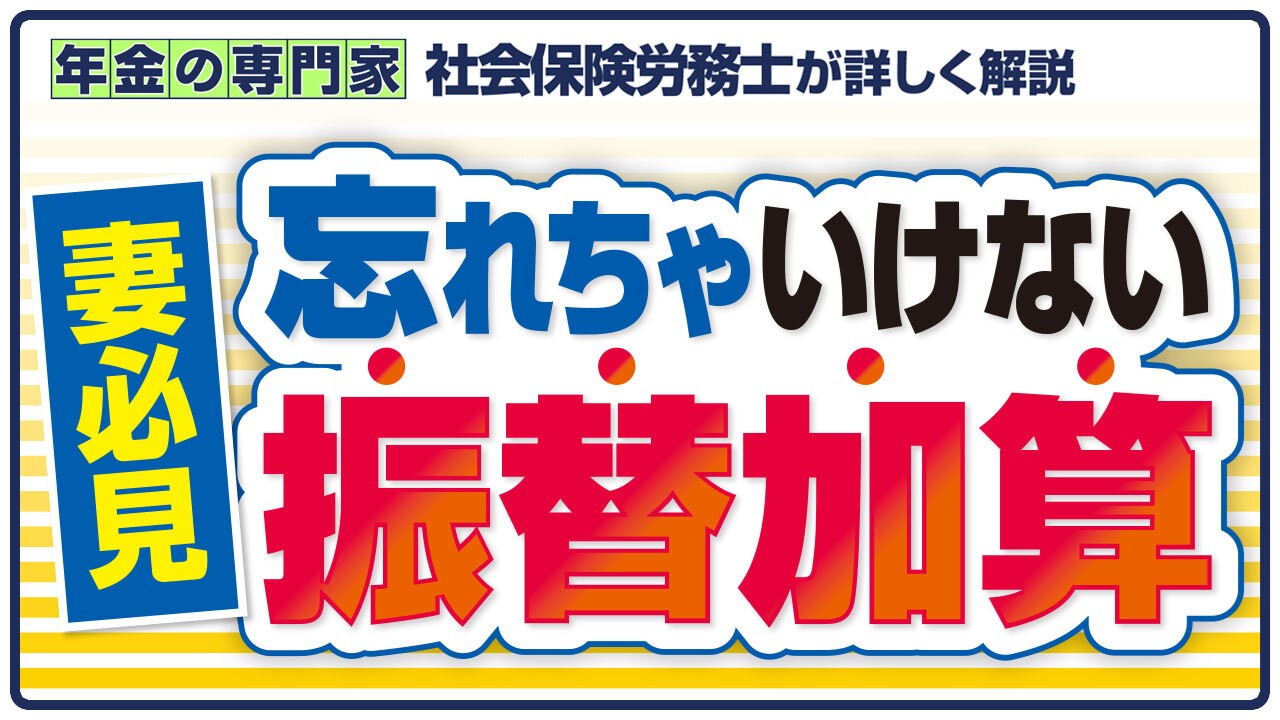

年金請求者の配偶者が厚生年金に20年以上加入している場合、請求者の名前の記入が必要です。
配偶者の名前ではありませんのでご注意ください。

年金請求者の年収が850万円未満なら「はい」に丸をします。
「いいえ」の場合は、年金事務所に相談しましょう。
18ページ目(扶養親族等申告書)

扶養親族等申告書を記入するページです。
老齢年金は年金額によって源泉徴収されます。
扶養親族等申告書を提出することで控除を受けることが可能です。
このページの記入方法は細いので、記入する必要がない人をご説明します。
記入が不要な人は以下の通りです。
- 65歳未満で年金額が108万円未満
- 65歳以上で年金額が158万円未満
- 扶養親族等がいない、かつ年金受給者自身が障害、寡婦に該当しない場合
- 確定申告する場合
- 給与所得等で配偶者控除や扶養控除を受ける場合
記入が必要な方は年金事務所で確認をしてください。
年金請求に必要な添付書類

次は、年金請求に必要な添付書類を説明します。
年金振込口座を確認できる書類

年金振込口座を確認できるものをご準備ください。
たとえば、通帳の表紙裏側にある名前などが記載されているページをコピーするとよいでしょう。
キャッシュカードのコピーでも問題ありません。

年金請求書の1ページの口座証明欄に銀行から証明印をもらっている場合、口座確認書類の添付は不要です。
雇用保険の被保険者番号を確認できる書類

6ページで書類雇用保険の番号を記入した人は添付が必須です。
- 雇用保険の被保険者証の写し
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 高年齢雇用継続給付支給決定通知の写しなど
雇用保険の被保険者証はハローワークで再発行ができます。
戸籍・住民票関係の書類

次は戸籍・住民票関係です。
間違いやすいところなので最初にお伝えすると、マイナンバーが登録されていても戸籍謄本は省略できません。
省略ができるのは住民票や課税証明書のみです。
戸籍の添付が必要な人
戸籍の添付が必要な人は、年金請求者または配偶者が厚生年金に20年以上加入している人です。
また、今後20年以上の加入が見込まれる人も必要です。
添付する戸籍謄本を取得するタイミングは?
添付する戸籍謄本は、請求前6ヶ月以内に取得したものが有効です。
メモ
ただし人によって違いがあるので、受給権が発生した誕生日以降に取得するのが無難といえます。
マイナンバーで住民票や課税証明書の省略を希望する場合
マイナンバーで住民票や課税証明書の省略を希望する場合、マイナンバーが登録されている人は何も添付する必要はありません。
登録されていない人は、マイナンバー確認書類と身元確認書類が必要です。
マイナンバー確認書類は以下の通りです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバー入り住民票
いずれかのコピーが必要になります。
身元確認書類については、日本年金機構の資料からご確認ください。
年金請求後の流れ

請求手続きが終わると約1ヶ月程度で年金証書が届きます。
さらに12ヶ月後に年金振込通知書、年金支払通知書が届いて支払い開始です。
請求手続きをしてから支払いまでは3ヶ月ほどかかります。
まとめ
今回は年金請求書の書き方を解説しました。
ほとんどの方は1ページから順に見ていただければ請求書の記入は簡単に済みます。
場合によっては年金事務所への相談が必要なので、ご自身が該当するかどうか確認してみてくださいね。
最後に、監修を務めた「60歳からの年金大改正で損しない本(100%ムックシリーズ)」が好評発売中です。